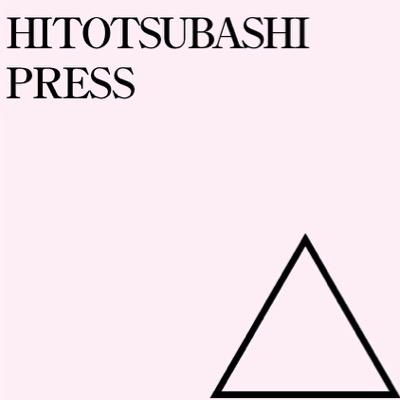<blockquote>
「自治の鐘高鳴りひびく―」本学の校歌「武蔵野深き」には、このような一節がある。しかし「自治の鐘」は今、危機に瀕している。一橋新聞部を含めた6つの団体から構成される自治団体連合(以下、自団連)に対して、毎年分配される自治団体連合費(以下、自団連費)が、今年度、例年より8割以上減額される見通しとなったのである。このままでは、学園祭や課外活動団体の活動に、甚大な影響を及ぼしかねない。
まずは自団連の一所属団体として、まだ自団連費を納入していない学生には、納入をお願いしたい。自団連に所属する団体は、学園祭の運営、新歓期のイベント開催、各部活・サークルの取りまとめを担うなど、どれも学生全体にとって有益な取り組みを行っている。そしてこれらの取り組みは、学生一人一人から頂いた自団連費なくしては成り立たないものである。こうした趣旨をご理解の上、ぜひご協力を賜りたい。
自団連費の集金・分配を担う学部協議会によれば、自団連費の納入率は、コロナ禍に見舞われた2020年度以降、低迷が続いているという。新入生歓迎委員会の協力の下、新歓期には新入生向けに、自団連費の重要性を呼び掛けているものの、「コロナ・ショック」を脱却できないでいる。この背景には、自団連費をめぐる不透明性があるのではないだろうか。
そもそも自団連費の役割自体が、多くの学生に理解されていない可能性がある。4月に新入生向けに配られる「自治団体連合費納入のお願い」と題されたプリントには、自団連と自団連費について、数行程度の説明が記載されているのみである。納入することで具体的にどのようなメリットがある(あるいは納入しないことでどのようなデメリットがある)のかを明示することで、新入生は自団連費の重要性を、より実感的に理解することができるだろう。
また、自団連費の役割そのものは理解していても、その運用方法が不透明であるという理由で、納入を控えるケースも想定される。この点について、学部協議会は近年、本紙紙面において前年度の会計報告を行っている。しかし、各団体に分配された後の自団連費の使途公開については、団体それぞれの会計報告に委ねられている。これらを、学部協議会の会計報告と併せて公表してはどうだろうか。その際には、本紙紙面への掲載のみならず、場合によっては大学とも協力して、より幅広く学生に公開することを検討すべきだろう。
さらに、学部協議会の活動の透明性を高めるために、自団連所属団体から最低1名ずつを会員として出したり、自団連に関係しない学生に数名参加してもらい、第三者的視点を取り入れたりすることも一案だ。現状、学部協議会は特定の団体出身者が多くを占めており、このことは「密室政治」批判を招きかねない。
ここまで学部協議会、そして自団連の今後のあり方についていくつか意見を述べてきたが、一方で従来の姿勢からの転換が最も求められているのは、一橋新聞部に他ならない。自団連に所属する唯一の報道機関であるにもかかわらず、自団連費をめぐる窮状を、今日まで大きく報じてこなかった責任は、決して小さくない。このことをすべての部員が肝に銘じ、自団連の動きについて、今後も追い続けていく必要がある。それだけでなく、種々の改革を自ら率先して実行し、学部協議会や自団連に提言していく姿勢も欠かせない。インターネット上を中心に、新興の学内メディアが続々と登場する中で、学生から集めたお金を元に紙面を発行している身としての責務が、改めて問われているといえよう。
もっとも、これらの改革を実行して自団連の透明性を高めた上でも、自団連費の納入率が向上しないようであれば、それはもはや、自団連という枠組み自体に疑問が呈されているといえるのかもしれない。この場合、現在の枠組みを根本から問い直し、学生の多くが望む形へと変化させていくことが「学生自治」の本旨に沿うといえよう。いずれにせよ、すべての学生を巻き込んで、自団連のあり方を議論する時期に来ている。今や鳴りを潜めた「自治の鐘」の音を再び聞くことができるか否かは、学生一人一人の意識にかかっている。
</blockquote>